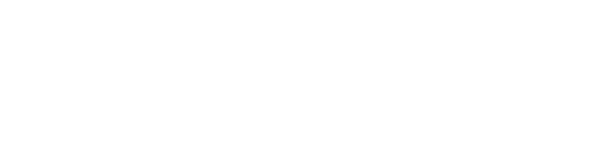大切なのは「日本語力」:高橋知伽江さん(脚本、翻訳家)インタビュー
世界にはばたく卒業生

ディズニー映画『アナと雪の女王』に登場する「ありのままの」というフレーズの生みの親であり、現在はオリジナル?ミュージカルの脚本執筆を中心に活躍されている高橋知伽江(たかはしちかえ)さん。(本名:高橋由美子さん、外国語学部ロシヤ語学科(以下、ロシア語科)卒業)
今回はそんな高橋さんにご自身の学生時代やお仕事、演劇界について深くお話しいただきました。
取材担当:国際社会学部イベリア地域3年?恩田はな(おんだはな)
演劇への興味と学生時代
―――はじめに、ご自身の専攻語としてロシア語を選んだ理由を教えてください。
高校時代にチェーホフ(ロシアの劇作家)のお芝居を何本か観て、それをきっかけにロシアの文学作品に興味を持つようになったためです。私の母が演劇好きで、一緒に観劇をする機会が度々ありました。幼いころは子ども向けの舞台を観ていたのですが、高校生くらいになると大人向けの芝居も観るようになって、そこでチェーホフを知りました。
―――お母様の影響で幼いころから演劇に触れる機会があった、というわけですね。素敵です!

―――続いて、学生時代の様子についてお伺いします。当時の東京外大での勉学や授業の様子はどのようでしたか。
今の様子は分かりませんが、当時は少人数のクラスでロシア語を勉強していました。大学に入学してからロシア語を学び始めたので、最初はとても大変でした。巻き舌音などといった発音から始まって。あと、当時ロシア語科は留年する学生が多い語科だと言われていたのもあって、同級生の中にも大人な雰囲気の学生が混じっていたのが印象に残っています。私は真面目に勉強した方だと思いますが(笑)。
―――在学中はロシア語劇団コンツェルトというサークルに所属していたと沼野恭子教授(本学大学院総合国際学研究院)から伺いました。
そうですね。当時は東京外大と早稲田大学、東京大学でロシア語を勉強している学生が集まって、年に1回ロシア語劇を公演するために合同練習を行うサークルでした。団体自体はこの3大学でロシア語を教えていらした野村タチアナ先生がつくられたものです。私の学生生活はほとんどこのコンツェルトに明け暮れたように思います。そもそもロシア語学習人口が少ないというのもありますが、数少ない学生のロシア語学習者がここに集まることで、学生たちの間で新たな交流が生まれていましたね。
―――当時高橋さんはコンツェルトでどういった役割を担当していたのでしょうか。演劇となると脚本や演出、役者、照明などさまざまな担当がありますが。
脚本は既にあるものを使っていました。私は比較的裏方気質でした。舞台に出たこともありますが、基本的には裏方の仕事を担当しました。演出をやったこともあるし、プロンプター(台詞や所作を忘れた役者に合図を出し、思い出させる役割)だったこともあります。それから、2年生の時にやったチャイコフスキーのオペラ『エフゲニー?オネーギン』では、当時同じくコンツェルトのメンバーだった沼野恭子教授が全編ピアノを演奏していらっしゃいました。
―――では、当時は脚本を書くことにはあまり関心がなかったのでしょうか。
はい、その頃は全くそういったことは考えていませんでした。そういう思考がなかった。コンツェルトも東京外大の友達が入ると言うからくっついていっただけなので…。勉強になるからと、サークル主宰のタチアナ先生とロシア語で話をしているうちに、なんとなくサークルにも参加していきました。ただ、舞台への愛情といったものはコンツェルトでの活動から今に至るまでつながっている気がします。

就職と退職 「演劇を仕事にするとは思わなかった」
―――東京外大卒業後は劇団四季にて勤務していたとのことですが、どのような理由、経緯で就職を決めたのでしょうか。
卒業してすぐ、劇団四季に就職したというわけではないのですが…。卒業した時は収入の面から考えて、演劇に関わる仕事に就くという選択肢はなく、とりあえず就職はして、お芝居はこれからも楽しく観るもの、という考えでした。なので、まずは普通の就職活動をして、一般企業のシンクタンクに勤めました。当時は働く女性に対する考え方や体制も古く、女性の仕事はコピーとり、お茶くみがメインでした。で、あっという間に挫折して(笑)。就職して1年くらいで朝起きるのも嫌になってしまうほどでした。
かといって他にやりたいことがあったわけでもなく、その頃から演劇に関わる仕事ができないだろうか、と考えるようになりました。そこで、当時東京外大でロシア演劇を教えていらした佐藤恭子先生に相談に行きました。先生は「あなたみたいな素人が演劇界で働けるわけがないでしょ」とおっしゃったのですが、その時たまたま先生のデスクに劇団四季のファン向けの機関誌があり、そこに当時の社長の秘書を募集する広告が出ていたのです。概して収入が安定しないとされる演劇界において、劇団四季は月給制だったということもあり、先生は私に(劇団四季の採用試験を)受けてみたら、と提案してくださいました。また当時、劇団四季はチェーホフをやっていて、私自身も劇団に対する興味、関心があったので、採用試験を受けに行きました。その結果、採用が決まり、働き始めたのです。
―――なるほど。一度一般企業に勤めて、そこで改めて自分の働き方や本当にやりたいことが分かったからこそのキャリアですね!
美しく言うとね(笑)。私の人生、ずっと「偶然」の連続です。何か目指すものがきっちりあったわけでもなく、ただただ流されてきたのだけれど…。でも、そういった偶然も運命のようなものなのかもしれませんね。
―――現在はフリーランスという形で働かれていますが、そうなったきっかけなどはありますか。
先ほど申し上げたように、劇団四季には社長の秘書として就職しました。社長は劇団四季の創設者でもあり、演出家でもあったため、演出の仕事をする時は私も稽古場について行きました。そこで初めてプロによる演劇の稽古を間近で見てとても興味をもち、秘書としての仕事が終わっても、帰らずに稽古場にずっと張り付いていたんです。そんな私を面白がってか、ある日、演出家がその時稽古していた演目の台詞の一部を変更したい、考えてきてくれ、と私に言ったのです。私は一晩台詞を考え、翌日その新しい台詞を稽古場で俳優がしゃべってくれて。それを聞いたときに、これは面白いな、と思いました。(自分の考えた)言葉が役者の声を通して命をもつ瞬間というのを目の当たりにした時に、これはすごく面白いなと。当時24、25歳くらいだったと思いますが、この時からこういうことをやってみたいな、と思い始めたような気がします。
また、東京外大卒だから(本当はそうじゃないのに)英語ができると思われ(笑)、演出家から翻訳をやってみろ、訳詞(歌詞を翻訳すること)をやってみろと言われるようになって。当時、本当はどちらも自信がなくてやりたくなかったのですが…(笑)。でもノーと断ることができる状況ではなかったので、ぽつぽつとやり始めた、という感じです。仕事を通して勉強させてもらいました。
フリーランスとして脚本や翻訳の仕事がやりたくて劇団をやめたというわけではないのですが、劇団で仕事をしていた時に知り合ったディズニーの方から運よくお仕事の依頼を受けたのです。その仕事をやって、また次のお仕事につながっていき、今にいたっています。
―――お仕事の際、大学での学びや経験など、学生時代に得たものが活きているな、と感じることはありますか。
ロシア語科という小さいクラスでのつながりやコンツェルトでの人間関係というのは、今でもとても大切なものだと思います。仕事に関して言えば、日露戦争時のロシア人捕虜と日本人看護婦の恋愛を描いたミュージカルを執筆したことがあるのですが、それがロシアで上演された際は、ずいぶんと東京外大の友達に助けてもらいました。ロシア語字幕を作る時に「こういう時は何格だっけ?」とロシア語に関して同級生に相談して話し合って(笑)。
―――確かに、こういった助け合いやつながりは東京外大ならでは!という感じがしますね(笑)。

―――続いて、お仕事に関する具体的な質問です。訳詞(歌詞を翻訳すること)はどのような工程で行うのでしょうか。本や記事などいわゆる「文章」を訳す時との違いをお伺いしたいです。
訳詞は、普通の翻訳とは全く違うと言っていいほど、違うものです。まず、音楽を聴き込んで作詞家と作曲家が何を一番伝えたいと思っているのかを理解します。そのうえで訳詞を進めていきます。あと、例えば本だと人名に続けてかっこ書きで「○年の詩人」、といった注釈を付け加えることができますが、舞台上の歌詞や台詞であればそれはありえないわけです。本などの文章を訳す時と舞台の言葉を訳す時の大きな違いは、耳で一度聞いただけで理解できる言葉にするという点にあると思います。
―――訳詞となると、単語の長さや言葉選びなどといった点も留意する必要があると思うのですが、そういった点で苦労する部分はありますか。
はい。英語の場合ですと、1つの音に1音節入ります。例えば「Thank you」と言う場合はthank、youと、2つ音符があれば収まるのですが、日本語の場合は1つの音符に1音が原則となっているので、「ありがとう」とすると5つ音符が必要になってしまいます。また、英語だと自分のことは「I」と1つの音符で言えるのに対して、日本語だと私、俺、僕などさまざまな言い方があり、ものによっては英語の2、3倍の音が必要です。これが映像作品の訳詞となると、さらに歌っている人物の口の動きにも気を配らなくてはいけないので、制約だらけです。訳詞は作詞家と作曲家が伝えたいことのエッセンスを音符にのせるので、直訳の意味が入らないことが多いです。この曲において絶対に伝えなくてはいけないことは何か、作詞家は何を言いたいのか、作曲家はどこのメロディーで何を一番訴えようとしているのかを考えて、訳詞をする必要があります。
そういった意味では、訳詞は作詞と同じようなものだと思っています。作詞されたものを、新たに日本語で作詞しなおす、という感じで。なので、語学力よりは「日本語力」の方が大切ですね。
―――なるほど。この「日本語力」をつける方法や心構えなどはありますか。
日本語は私たち日本語母語話者にとっては日常的に使っている言語ですから、普段は何も考えずに話したり書いたりしていると思うのですが、まずはそこに意識を向けることが大事だと思います。例えば最近は「ら抜き言葉」を使う人が多くいますが、そういった言葉遣いに気づく、といったことでしょうか。言葉に対する感覚というものを意識的に持つことが大切なので。平凡ですが、この「日本語力」をつける具体的な方法としては読書があります。翻訳されたものではなく、日本人が日本語で書いた文学作品を読むことをおすすめします。翻訳された作品は、必ずその元の言語の性格が残っていますので。
―――今のお仕事で楽しいこと、大変なことを教えてください。
最近は翻訳よりもオリジナル?ミュージカルを書くことが多く、それはもう大変なことばかりです(笑)。楽しいことといえば、公演初日が無事開いて、お客さまが喜んでくださっている姿を見ることですね。それで全部報われるからこそ、また修羅場の仕事をやるのだと思います。オリジナル?ミュージカルは、作家と演出家、作曲家、プロデューサーとがチームを組んで作っていく総合芸術ですが、いつもその4人の意見が合うわけではないということが、大変な点でしょうか。時には喧嘩もしながら話し合って、作品によっては3年もの長い月日をかけて創り上げていくのですが、その過程は楽しくもあり、苦しくもあります。脚本を担当する時は、稽古前にも稽古中にも幾度となく書き直しが必要になります。
ただ、「(仕事が)嫌だ」という気持ちにはなりませんね、もちろん辛いこともありますが。特に作家の場合は創作のトップバッターなので、私が脚本を書かなければ、作曲家や舞台美術や衣装、照明などのプランナーが動けません。脚本は作品の最初の設計図なので、そこがこけるわけにはいかないのです。

これからの舞台芸術
―――今後、日本の舞台産業や演劇文化はどのように変化していくと思いますか。
このコロナ禍を通じて演劇界で一番変わったのは輸入物(海外で制作された作品)に対する見方だと思います、特にミュージカルは。海外作品を日本で上演する時、これまでは基本的に演出家などの海外スタッフを日本に招へいしてきました。これは1つの作品をパッケージとして買い取り、演出や照明、振り付けなどすべてにおいて海外で上演されているものと同じにする必要があるためです。ですから、上演の度にその作品のクリエイティブチームに日本に来てもらわなければいけない。それが、コロナの影響でできなくなってしまったんです。また、海外の作品は権利の関係上、映像配信もできません。このパンデミックを通じて、日本の演劇界は輸入に頼っているととんでもないことになる、と思い知らされたわけです。
そのため、今日本ではオリジナル作品の創作に舵を切りかえつつあります。そういう意味では、このコロナ禍は痛かったけれども、いい意味で日本の演劇界に影響を与えたように思います。今後は国産の作品がより多く制作、上演されていくのではないでしょうか。
―――日本で作られた作品がこれから海外にいく、という可能性はあると思いますか。
あると思います。最終的にはそうあらねばならないとも思うし。ただ、現地で日本の作品を上演できたとしても、それを興行として成立させるのはまだまだ遠い話です。いろんな問題を乗り越えてゆく推進力が、日本の演劇界には必要だと思います。

―――本日はお仕事の話を中心にお話しいただきましたが、将来に向けて学生時代にしておいた方が良いことがあればぜひ教えてください。
就職に関して言えば、今はインターンシップのような会社の様子を知る機会がたくさんありますよね。そういったものに参加するといいのではないでしょうか。私は学生時代に家庭教師のアルバイトしかやったことがなくて、最初はいわゆる企業というものをあまりよく知らない状態で就職しました。なので、当時は企業において女性という存在はどのように扱われているのか、女性であるだけでこうも不利なのかといったことを、就職してはじめて実感したのです。そういった点も含め、各企業がどういった風土なのかをあらかじめ学ぶことはとても大切なことだと思います。
また、アルバイト含め、学生のうちにいろんな体験をしておくといいと思います。具体的に言えば、学生という枠からはみ出した体験をしたほうがいいかと。そういった場を通じて人間関係を広げたり、社会で働く人を間近で見たりしてほしいです。
―――最後に東京外大生に一言、メッセージをお願いします!
東京外大生に限らず、若い人たちに伝えたいことになりますが…。自分の目の前にハードルが置かれたら跳んでみてください。私自身、大学卒業後に明確な目標があって社会に出たわけではありませんでした。最初の職場で行き詰った時にたまたま劇団に入り、そこで訳詞や脚本をはじめ、これをやってみろ、あれをやってみろとさまざまな課題を与えられました。自分で何かをした、というよりは目の前に置かれたハードルを跳ぶことによって前進してきたのです。
断崖絶壁から跳ぶのは危険ですが、ハードルに引っかかって転んでも大したことはない場合がほとんどです。できない、やりたくないと困難な状況を避けるのではなく、ハードルを置かれたら「もしかしたら」という気持ちをもって跳んでみた方がいいと思います。
私も、最初は自分に訳詞ができるなんて夢にも思っていませんでした(笑)。音楽の知識があったわけでもないし。でもその時やってみて、その適性を見抜いてくれた方がいたからこそ、今の仕事につながっているわけです。自分の適性は自分では分かっていないかもしれません。とりあえず目の前のハードルを跳んでみることで、そこに何か新しいものが開けるかもしれませんよ。
インタビュー後記
私自身、以前から舞台芸術やミュージカルに関心があり、今回このような形で憧れの存在であった高橋様とお話ができたことがとても嬉しかったです。「偶然ばかりの人生」とおっしゃっていたように、取材を通じて学生時代のご縁や不意に現れる機会のありがたさに改めて気づくことができました。現在私は派遣留学中なのですが、留学先での人との出会いやチャンス、危機をも今後の自分の糧としていきたいと強く思いました。
高橋様、この度は大変お忙しいところ誠にありがとうございました。
国際社会学部イベリア地域3年 恩田はな